高齢者の方は突然の病気やケガで入院する事ってありますよね。
しかも、お年寄りの場合、入院が長引くケースも多くあり「入院費が高くなったらどうしよう!?払えるかしら?」って悩んじゃいませんか?
特に初めての入院だとそんな風に悩んでしまいますよね。
でも心配ありません。実は私の母(80代)も何度か病院に入院した事があるのですが、いくつか工夫する事で入院費をグンと安くすることができましたよ。
今回の記事では「高齢者の入院費を安くする具体的な方法」についてお話ししますね。
高額療養費制度を使えば医療費が驚くほど安くなる!!
老人の入院費を少しでも安く押さえたい人はぜひ参考にしてください(^^)
高額療養費制度とは
75歳以上(認定を受けた65歳以上の人も)の、つまり後期高齢者が、手術とか入院とかで、医療費が高額になった時に、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度のことです。
これは別に、75歳以上(認定を受けた65歳以上の人も)だけじゃなくて、子どもから適応される制度なのですが、今回は、後期高齢者75歳以上のお年寄りの入院・医療費を安くする方法をお話ししますね!
私の母が一回目の入院をする時に、病院の人から、「「高額療養費制度」というものがあるので、申請してくださいね。」と言われました。
なんと、医療費には自己負担限度額というものがあって、年齢や所得に応じて、それを超えた場合は、月毎に自己負担限度額を超えた金額が払い戻されるんです。
そんな高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)制度というものをうまく利用して、医療費をできるだけ安くしましょう。
まずは、自己負担額と自己負担限度額はどうなっているのか?具体的に紹介しますね。
自己負担額と自己負担限度額とは
下の表が1割負担と3割負担の場合の1ヶ月の自己負担額の表です。(※ スマホの人は画面を横にして見てくださいね♪)
ご自身の適用区分は、被保険者証、高齢受給者証を見れば確認できますよ♪
■平成29年8月診療から平成30年7月診療まで
負担割合
所得区分 外来 (個人ごとの限度額)
外来+入院 (世帯ごとの限度額)
3割
現役並み所得 57,600円 80,100円+ (10割分の医療費
-267,000円)×1%
<44,400円※2>
1割
一般 14,000円 ※1 57,600円 <44,400円※2>
区分2 8,000円 24,600円 区分1 8,000円 15,000円
■平成30年8月診療から
負担割合 所得区分 外来 (個人ごとの限度額)
外来+入院 (世帯ごとの限度額)
3割
現役並み所得3 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% <140,100円 ※2>
現役並み所得2 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%<93,000円 ※2> 現役並み所得1 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%<44,400円 ※2> 1割
一般 18,000円 (144,000円 ※1)
57,600円 <44,400円 ※2>
区分2 8,000円 24,600円 区分1 8,000円 15,000円 ※1 1年間(毎年8月1日~翌年7月~31日)の外来の自己負担額の上限額は、144,000円となります。
※2 過去12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる外来+入院の限度額(多数回該当)。ただし「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。
なお、平成30年8月診療からは現役並み所得の「外来(個人ごと)」が廃止されるため、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当に含みます。
*区分1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。
*現役並み所得者の方とは、課税標準額が145万円以上の方(ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば区分は「一般」となります)。
*区分2の方とは、世帯員全員が住民税非課税である方。
*区分1の方とは、世帯員全員が住民税非課税であって、年金収入80万円以下(その他の所得がない)及び老齢福祉年金受給者。
*75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険(国民健康保険、会社の健康保険など)と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。
引用元:町田市ホームページ 後期高齢者医療制度の給付関係について
う~ん、これを見ただけじゃ、ちょっと分かりにくいですよね^^;
では、高額療養費制度を使って自己負担限度額がどのようになるのか? 入院費をどれくらい安くすることができるのか?
実際の例で紹介します。
高額療養費制度を利用して入院費が1/3になった母の場合
私の母が高額療養費制度を使ったら、1ヶ月あたりの入院費(1回目)が、実際に掛かった入院費(自己負担額)の約1/3で済んじゃったんですよ!!
母は、平成29年11月から平成30年2月まで骨折で入院したのですが、そのうちの1ヶ月の入院費を例にとって説明しますね。
入院1ヶ月の入院費の総額が83万円。母の健康保険は3割負担なので、病院からの診療費の請求書は、約25万円でした。
1ヶ月で25万円はさすがにきついですよね・・・。

そこで、入院費を安くする方法として、高額療養費制度を利用したんです。
それを利用して、実際にどれくらい安くなったのかを紹介しますね。
内訳を計算式で紹介すると、だいたいこんな感じです。(※細かい端数は除きました。)
と、実際に支払ったお金が85,730円でした。
高額療養費制度を利用したお陰で、病院に支払った25万円から、上で計算した自己負担限度額を差し引くと、
これってすごくないですか?
25万円のうち、164,270円も戻って来たという事ですよ!
|
1ヶ月の入院費の総額 830,000円 |
||
|
病院に支払った額 250,000円 |
健康保険分 580,000円 |
|
|
自己負担額 85,730円 |
高額療養費支給額 164,270円 |
|
これはもう、高額療養費制度を利用しない手はないですよ!
では、実際に高額療養費制度にどうやって申し込んだらいいのかを説明しますね♪
高額療養費の申請のしかた
通常の場合、高額療養費支給の対象となった診療月の3~4カ月後に申請の案内と申請書が自宅に届きます。
申請書に必要事項を記入、押印のうえ、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当の窓口に提出してください。

認定されると、決定通知が届きます。
一度申請すると、次回からは自動的に指定の口座に振り込まれます。
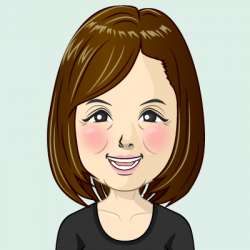
よく分からなければ、診察を受ける際、または入院をする時に、病院の窓口の担当者に「高額療養費支給」のことを聞いてみてくださいね♪ 必ず親切に教えてくれますよ。
高額療養費支給まで3~4ヶ月も待てない場合
高額療養費支給に申請して、晴れてお金が戻って来ると言っても、いったん病院へは請求額通り支払わなければならないのが辛いですよね。
でも、病院へ支払う時に1ヶ月の入院費が自己負担限度額の金額だけで良くなる方法があるんです!
どうするかと言うと、入院(外来診療でも)する時に、事前にお住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当の窓口に高額療養費支給を申請するだけです。
それをすれば、70歳以上の人は自動的に支払いが限度額までとなるわけです。
病院の支払い時に高齢受給者証か後期高齢者医療被保険者証を提示すれば、各自、支払限度額を支払えばいいんですよ♪
※ ちなみに、70歳未満の人は「限度額認定証」を発行してもらい、支払い時にそれを提示します。
注意!その1. 高額療養費の対象とならないもの
差額ベッド代・食事代・実費分
注意しなければないのが、入院費すべてがこの高額療養費支給の対象になるというわけではないのです。
つまり、差額ベッド代、寝衣やタオルなど、病院から借りているもの、オムツなどの実費分などは、自己負担になります。

なので、もし、有料のベッドを使っているのなら、その費用は、全額自己負担になるという事です。
健康保険+高額療養制度適応部分
・入院基本料(療養環境の提供および看護などにかかる費用)
・治療費(手術代、注射代、検査代、リハビリ代など治療にかかる費用)
自己負担部分
+差額ベッド代
+入院セットなど (患者用寝衣、バスタオル、タオル3枚、フェイスタオル2枚)
+・実費分(オムツ代など)
+食事代(これは入院日数や諸条件によって、割り引かれる場合があるので、病院の方に詳しく聞いてみてください。)
入院費を極力、安く押さえるのなら、この高額療養費の申請をして、部屋もできるだけ無料のお部屋にしてもらい、タオル、パジャマなど、必要なものはすべて自分のものを使いましょう。
入院費(医療費)が21,000円未満の場合
高額療養費は月単位で1つの医療機関でも、複数の医療期間でも、合算して21,000円以上の自己負担額を支払った場合のみ支払われます。
なので、入院費が21,000円に満たない場合は、高額療養費制度を利用することができません。
月をまたいでの入院費(治療費)の合算が自己負担限度額に達しない場合
高額療養費は月単位で計算される
ため、月をまたいでの入院(治療)での自己負担額の合算はできないのです。
なので、月またぎで高額な療養費になったとしても、それぞれの月で、自己負担限度額に達しない場合は、支給されません。
注意!その2. 高額療養費制度の申請は2年以内にしよう
高額療養費制度の申請期限は治療を受けた翌月1日から2年以内なんだそうです。
2年以上経ってしまうと時効になって、その入院(外来診療でも)の高額療養費は申請することができません。
また、高額療養費制度を1ヶ月以上利用したい場合は、毎月申請が必要になります。
私の母は、3ヶ月の入院となったので、月替りの頃に窓口の人がいつも「(高額療養費の)期限なので、また申請お願いしますね♪」と教えてもらい助かりました(^^)
注意!その3. 入院費(医療費)などの領収書はとっておこう
医療機関の領収書は、高額療養費の申請の時に必ず必要になりますので、大事に保管してくださいね。
無くしてしまったら申請できなくなってしまいます。
術後せん妄は本当に治るの?
高齢者の入院費を安くする方法のまとめ
それでは、簡単にこの記事のまとめをします。
-
- 高額療養費制度とは、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度のこと。
- 自己負担限度額は、それぞれの保険の適用区分によって違う。
- 高額療養費の申請は、入院費(医療費)支払い後にお住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当の窓口に申請書を提出する。
- 高額療養費支給まで待てない場合は、入院(外来診療でも)する時に、事前にお住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当の窓口に高額療養費支給を申請する。
- 高額療養費の対象とならないもの(場合)
・差額ベッド代、食事代、実費分
・入院費(医療費)が21,000円未満の場合
・月をまたいでの入院費(治療費)の合算が自己負担限度額に達しない場合
-
- 高額療養費申請をする上での注意点
・高額療養費申請期限は2年以内
・申請時には医療機関の領収書が必要
高齢者が入院費を安くするために高額療養費制度を利用することは、高齢受給者証か後期高齢者医療被保険者証を持っていれば、誰でもできます。
うちの母の入院費も、この制度を利用したお陰で自己負担額の1/3の金額に抑えられて、とっても助かりましたよ!
この申請さえすれば、高額な入院費(医療費)を驚くほど安くすることができるので、忘れずに申請してくださいね(^^)
【おすすめ】認知症を遅らせるには昔の話を話すのが鍵!そんな話を紹介しています。



